その他
職場における熱中症対策が義務化。事業者が知るべきポイントは?
- #熱中症
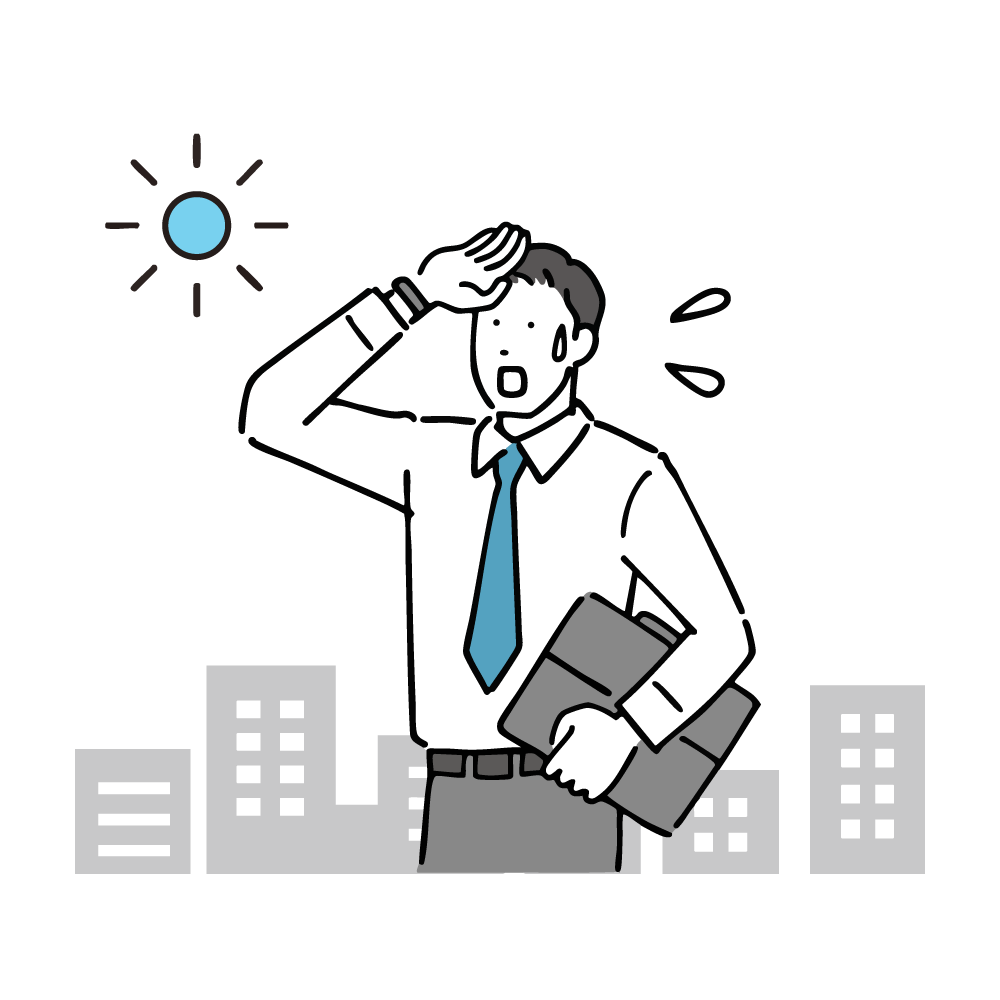
2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正に伴い、事業者に対して、特定の条件下における職場での熱中症対策が罰則付きで義務化されます。この義務化は、すべての事業者に影響を及ぼす重要な法改正です。
近年、夏の猛暑は年々厳しさを増し、職場における熱中症による健康被害や死亡事故が深刻化しています。
「知らなかった」では済まされない事態にならないよう、義務化の概要と事業者がとるべき具体的な対策をご紹介します。
====================
■なぜ変わるのか?
皆さんも感じていることだと思いますが、近年、日本の夏の平均気温は上昇し続けており、猛暑日や熱帯夜が状態化しています。
職場における熱中症による発症者数や死亡者数は増加傾向にあり、大きな社会問題となっています。厚生労働省によると、特に死亡災害は2年連続で30人レベルで、熱中症は死亡災害に至る割合が他の災害の5~6倍です。
「初期症状の放置、対応の遅れ」が主な原因とされており、これまで努力義務とされていた事業者の熱中症対策では、働く人々の命と健康が危険にされされる事態が多発していました。
このような状況を受け、国は労働者の安全をより確実に確保するため、熱中症対策を事業者の「義務」として明確化することを決定しました。
■何が変わるのか?
今回の労働安全衛生規則の改正により、事業者は「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際に、
以下の3つの措置を講じることが義務付けられます。
1. 熱中症の早期発見のための「報告体制の整備」
熱中症は早期発見・対応が重症化を防ぐ鍵となります。
そのため、熱中症の自覚症状がある作業者(本人)や、熱中症のおそれがある作業者を発見した者が
症状などを速やかに報告できる体制を整えましょう。
具体的には、連絡先や担当者をあらかじめ定め、現場で誰もがわかるように周知する必要があります。
特に一人作業や少人数作業の場合、報告手順や連絡体制の明確化が重要です。
2. 熱中症の重症化を防止するための「実施手順の作成」
熱中症の症状が悪化した場合の、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察・処置、緊急搬送先の連絡先・所在地など、具体的な対応手順をあらかじめ定め、文書化しましょう。
万が一の事態に備え、迅速かつ適切な対応ができるよう、具体的なマニュアルやフロー図を作成することが求められます。
3. 作成した体制・手順の「関係者への周知」
上記で整備した報告体制と、作成した実施手順を、関係するすべての作業者(労働者)に周知徹底しましょう。
現場で働く人が知らなければ意味がないので、定期的な教育や訓練などを行うとよいかもしれません。
-----------------
■「熱中症を生ずるおそれのある作業」とはどんな作業?
対象となるのは「WBGT(湿球黒球温度)28℃以上、または気温31℃以上の環境下で、
上記の環境下で連続して1時間以上、または1日当たり4時間以上の実施が見込まれる作業」です。
この作業を行う事業者は、熱中症対策が義務付けられます。
-----------------
■違反した場合どうなる?
今回の義務化には、罰則が伴います。
・熱中症対策の義務を怠った事業者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
・法人に対しても50万円以下の罰金が科される場合があります。
法的責任を問われる可能性があるため、事業者はこれまで以上に熱中症対策に真剣に取り組む必要があります。
====================
義務化された3つの措置だけではなく、
WGBT値の測定と管理、休憩場所の整備や冷房設備の設置などの作業環境の管理を行ったり、
暑い時間帯を避けて作業を行う、こまめに水分・塩分補給するよう促すなどの作業管理、
作業員の健康管理などを実施することも大切です。
自社の状況に合わせた熱中症対策を今一度見直し、作業員が安全で快適に働ける職場環境を確保しましょう。

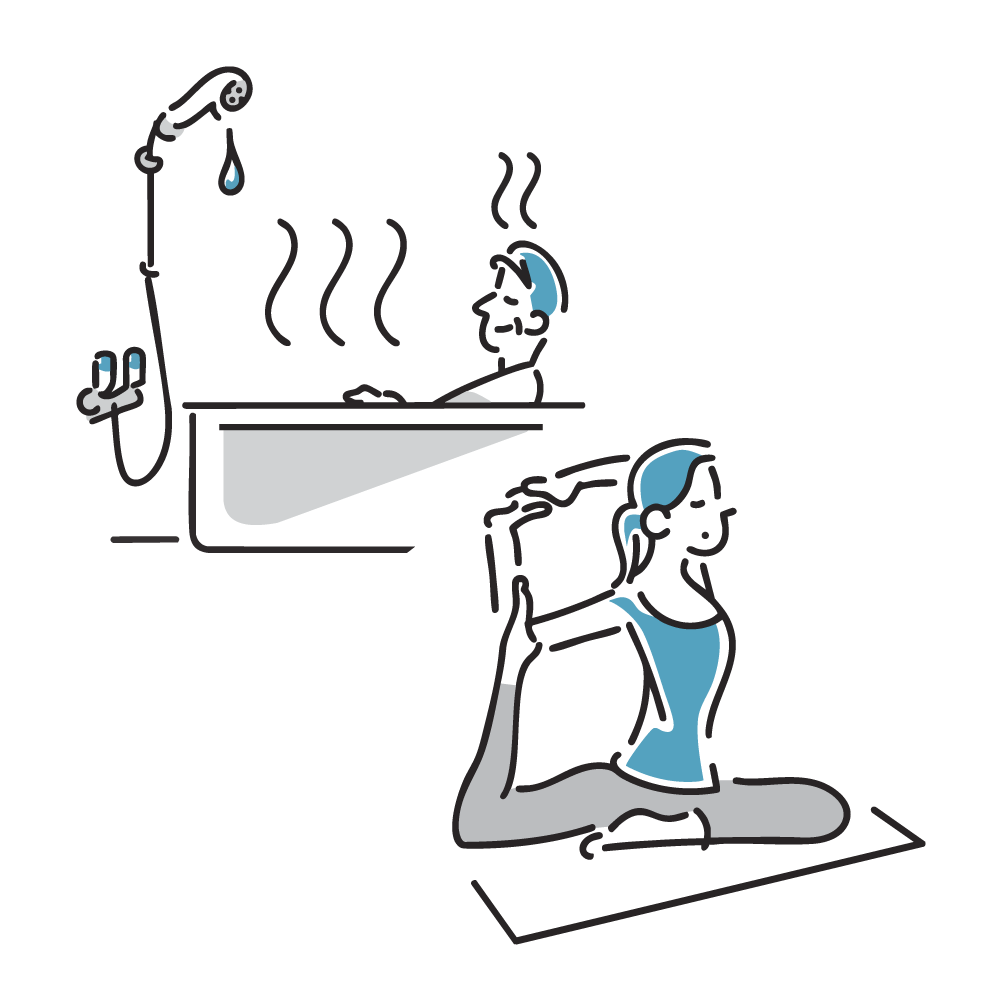
.png)