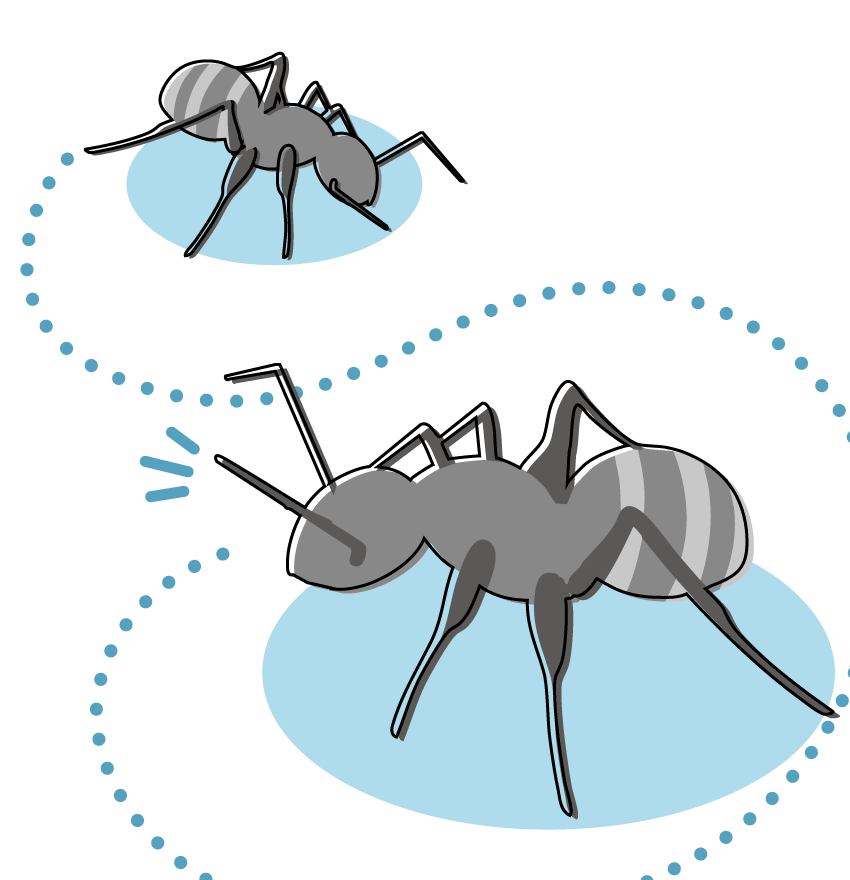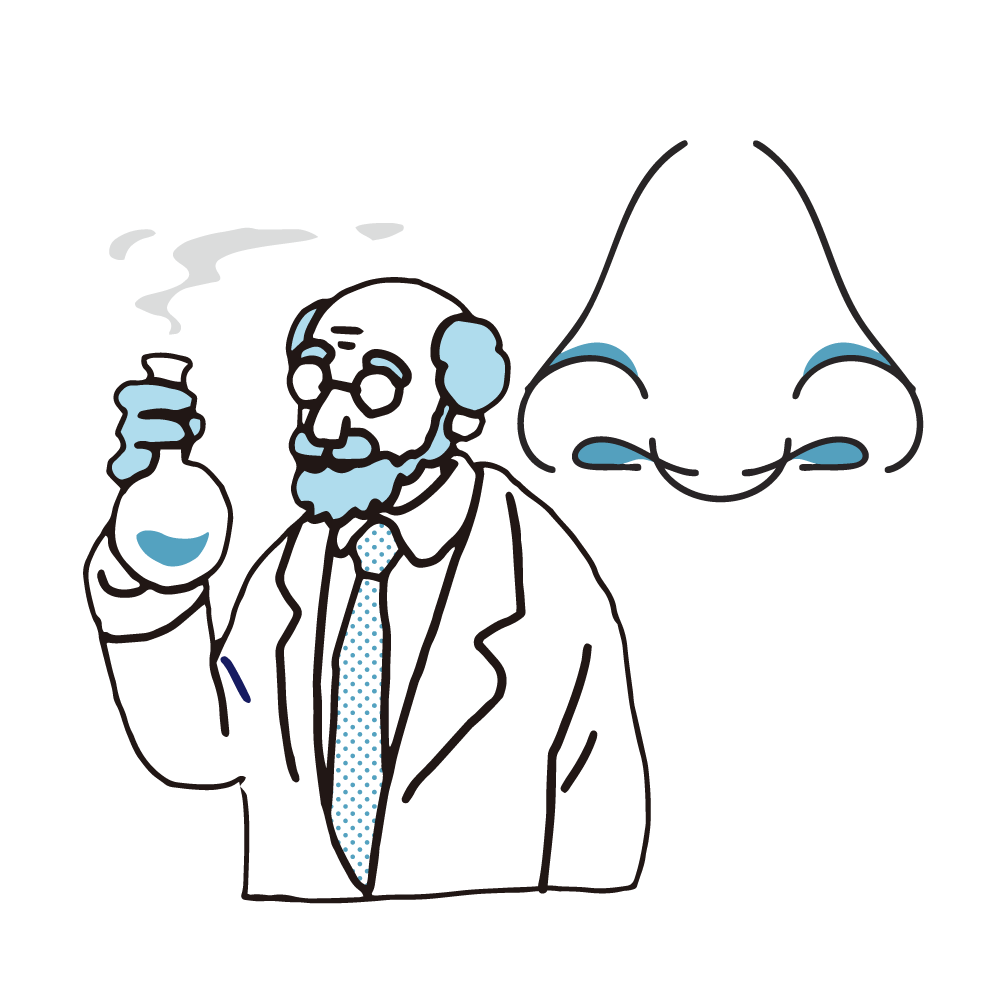においの話
悪臭と香水は紙一重
- #におい
- #臭い
- #匂い
- #脱臭
- #臭気物質
- #嗅覚
- #臭気判定士
- #臭気測定
- #悪臭防止法
- #特定悪臭物質
- #排気
- #脱臭装置
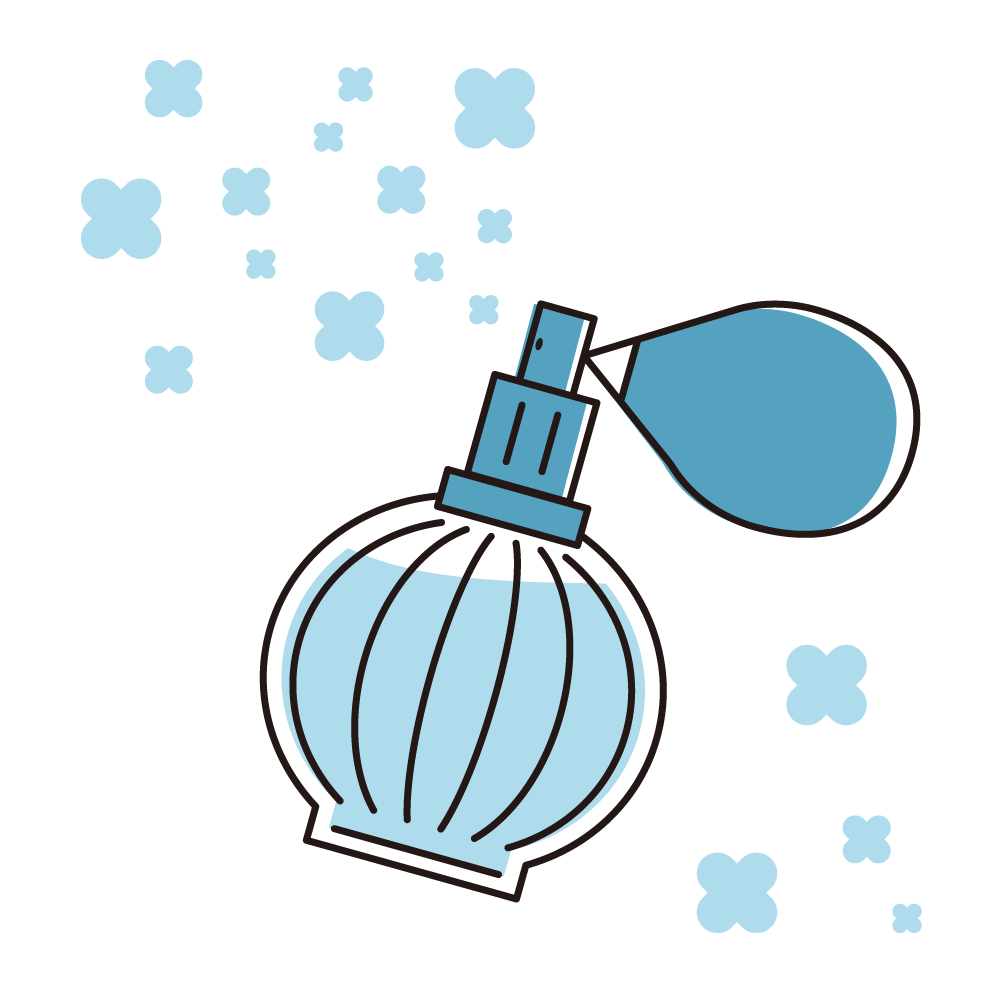
世界の香水市場規模は近年大きく成長しており、今後も数年にわたって成長が予想されています。背景にはアジアや中東などの地域において、所得の増加に伴い、香水を含む高級なパーソナルケア製品への需要が高まっていることが挙げられます。また、日本国内ではZ世代を中心とする若者のなかで、香水が単なる身だしなみではなく、ファッションやメイクと同様に個性を表現するアイテムとして認識されるようになりました。それにより、大手ブランドの香水だけではなく、独自の香りを追及する香水ブランドの人気が高まり、さらに自分だけの香りを作れるカスタマイズ香水にも注目が集まっています。
一方で、公共の場で香水などのにおいによる「香害」が、社会的な問題となっています。他人が身につけている香水や柔軟剤、芳香剤などの合成香料、いわゆる「いい香り」が不快感やさまざまな健康被害を発生させるという現象です。
今回は「いいにおいの香水」が「悪臭」と感じられてしまう理由を考えてみます。
まずは、香水という、合成香料が創り出した世界を覗いてみましょう。
多くの種類の合成香料を組み合わせて、いい香りを創り出していますが、組み合わせによってその香りは変わっていきます。1つの香料を単体で嗅いだ場合と、複数種類を組み合わせた場合には、違うにおいに変わる「変調」という化学変化も起こります。さらに、濃度が高い場合と低い場合とでも、においの質が異なる臭気成分もあります。
それでは、香水を創り出す合成香料の歴史をひもといてみましょう。古来より、香水はジャスミンやバラといった天然の植物、あるいは動物から採取される貴重な香料を用いて作られてきました。しかし、19世紀末に香水の世界に革命が起こります。
その立役者が、合成香料「クマリン」です。1882年にウビガン社が発売した「フジェール・ロワイヤル」は、このクマリンを初めて用いた画期的な香水でした。トンカビーンなどに含まれるクマリンは、甘くパウダリーな香りを持ち、天然素材だけでは表現できなかった新しい香りのカテゴリー「フゼアノート(シダの香り)」を確立しました。これは香水の歴史における、大きな転換点となりました。
クマリンの登場から約40年後、香水の世界はさらなる進化を遂げます。その主役となったのが、「シャネル N°5」で一躍有名になったアルデヒドです。
アルデヒドは「油臭い」「ワックスのよう」と表現されることもある多様な香りを持つ合成香料です。調香師エルネスト・ボーは、このアルデヒドを大量に使用し、それまで主流だった単なる花の香りを一変させました。アルデヒドはフローラルノートに「輝き」「複雑さ」「拡散性」を与え、香水全体をより遠くまで、より長く香らせることを可能にしたのです。この革新的なブレンドによって、「現代香水の母」と称されるシャネル N°5が誕生しました。
このアルデヒドという物質は、悪臭と香水は紙一重であることを説明するために、重要な物質と言えます。環境省が定める悪臭防止法では、「特定悪臭物質」22物質の排出が規制されていますが、そのなかに6種類のアルデヒドが含まれています。アルデヒド単体では嫌煙されるにおいなのですが、それを高濃度で配合し、他の香料と調合したシャネル N°5は「アルデヒド・カクテル」と呼ばれ、長年人々に愛され続けています。
ほかにも、香水と悪臭の関係に注目してみると、同様の特徴を持つ物質があります。
スカトール:高濃度では糞便臭として認識されています。極めて低濃度に希釈されると、ジャスミンなどのフローラルな香りの重要な構成要素となります。
インドール:こちらも糞便臭や獣臭を持つ一方、ジャスミンなどの花の香りを構成する大切な成分です。
ムスク:天然のムスクは動物の分泌物であり、高濃度では強烈な獣臭を発します。しかし、これを薄めると、官能的で持続性の高い香水成分に生まれ変わります。
このように、においの物質は濃度や組み合わせによって、私たちの脳に全く異なる印象を与えます。香水の調香がいかに緻密で科学的な作業であるかを物語っています。
香水の世界を悪臭との関係性から見てきましたが、いかがでしたでしょうか。クマリンやアルデヒドといった合成香料は、香水の歴史を大きく動かし、私たちの嗅覚体験を豊かにしてきました。そして、悪臭といい香りが紙一重であるという事実は、香りの科学の奥深さを教えてくれます。次に香水を手にする際は、その香りが持つ化学的な側面にも目を向けてみると、香りの世界がより一層面白く感じられるはずです。