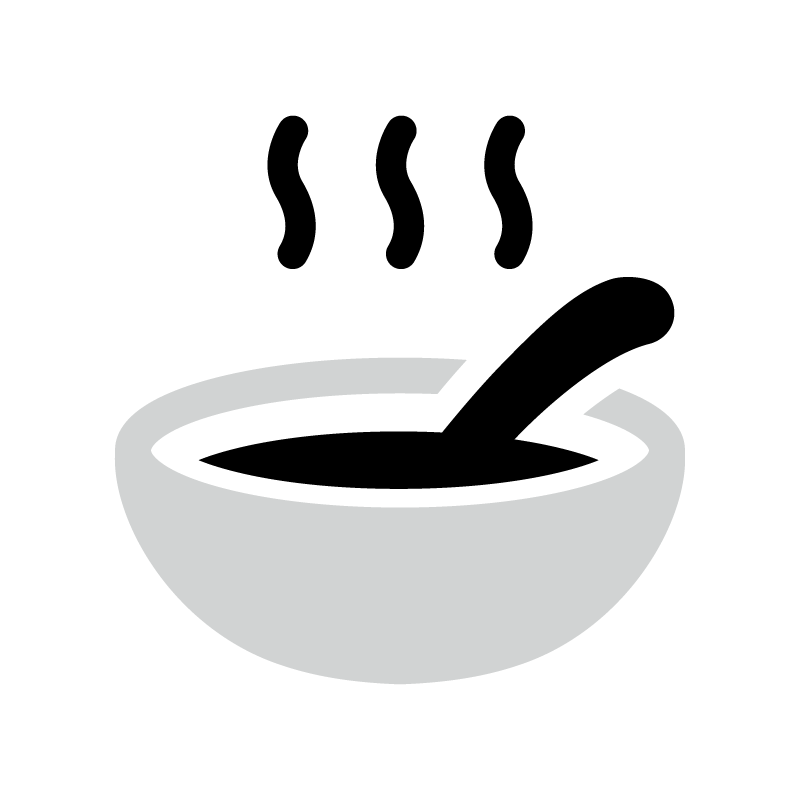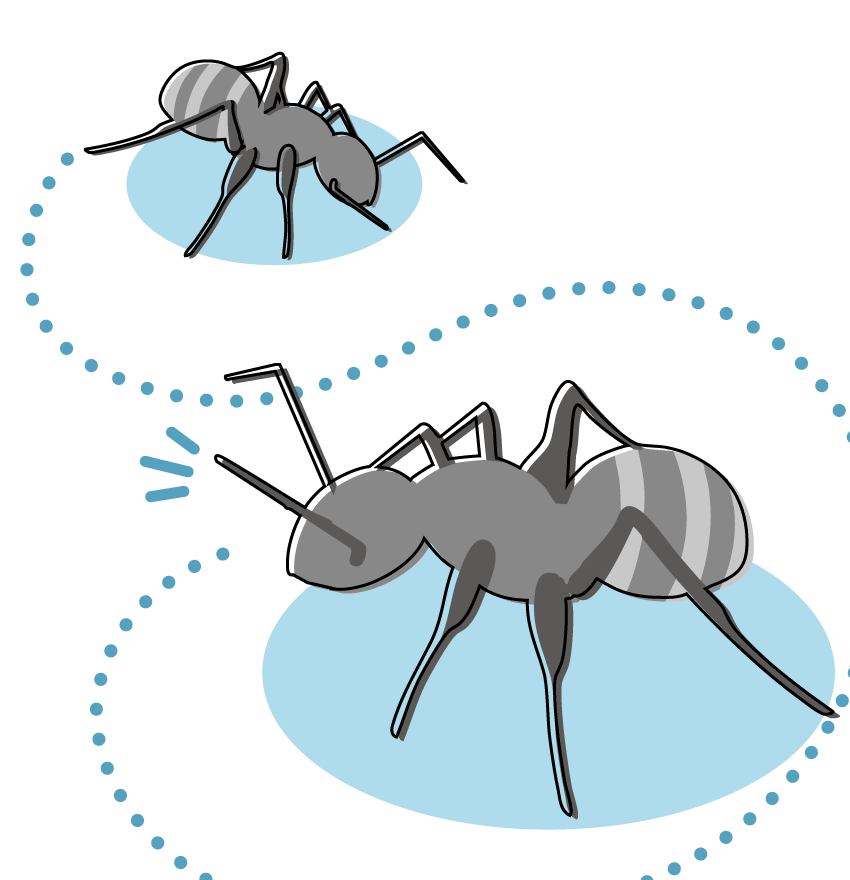においの話
夜になると街が臭くなる?
- #におい
- #臭い
- #脱臭
- #臭気物質
- #嗅覚
- #臭気判定士

「夜になると、街中が臭くなる」と感じた経験はありませんか?
昼間は特に気にならなかったにおいが、夜間や早朝になると顕著になることがあります。時には、大きな異臭騒ぎとなり、消防車が出動する事態に発展することもあります。原因が特定できれば迅速な解決が望めますが、原因が掴めない場合は対策を講じるのが難しくなります。
日中に感じなかったにおいを夜から朝にかけて強く感じる現象について、工場や事業所から排出される臭気がどのように拡散していくのかを知ることで、その理由が分かるかもしれません。
一般的に「街中が臭い」と感じる時は、排出された臭気が希釈されないまま、地表付近に留まっている状態です。これは空気の動きが少ないため、臭気が広範囲に拡散せずに高濃度のまま私たちの鼻に届くことが原因です。
それでは、通常排出された空気はどのように拡散していくのでしょうか?
まずは、晴れた日の昼間の臭気の拡散について見てみましょう。日中の地表付近の空気は、太陽光によって暖められ、上空の冷たい空気よりも温度が高くなります。暖かい空気は上昇する性質を持つため、地表付近で発生した臭気を含む空気は上空へと拡散していきます。上空へ行くほど空気の温度が下がるため、温度差によって空気の垂直方向の混合が活発になり、臭気は広い範囲に薄められていきます。そのため、日中は臭いを感じにくいのです。
一方、夜間になると、地表の熱は放射によって失われ、地表付近の空気は冷やされます。すると、上空の比較的暖かい空気よりも冷たく重くなるため、下降気流が生じにくくなります。また、風も弱まることが多いため、空気の水平方向の動きも鈍くなります。その結果、工場や事業所から排出された臭気は、拡散されにくい状態で地表付近に滞留しやすくなり、「夜になると街が臭い」と感じる原因となるのです。
また、早朝に臭くなることもありますが、この場合は「逆転層」が生じている可能性があります。これは、臭気を含んだ空気が上空に上がったにも関わらず、朝日によって地上の空気が暖められることで、大気が不安定になり、臭気が拡散されないまま地上に戻ってきてしまう現象です。
このように、昼間と夜間で異なる大気の安定度や風の有無が、臭気の拡散に大きく影響を与えています。工場や事業所においては、このような臭気の拡散メカニズムを理解し、排出のタイミングや方法を工夫するなど、周辺環境への影響を最小限に抑える対策が求められます。