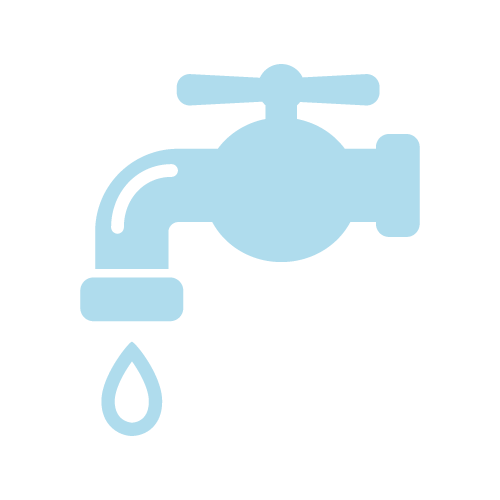オゾンの話
オゾンの恩恵と危険性
- #脱臭
- #殺菌・除菌
- #ウイルス不活化
- #オゾン
- #オゾン水
- #オゾンガス
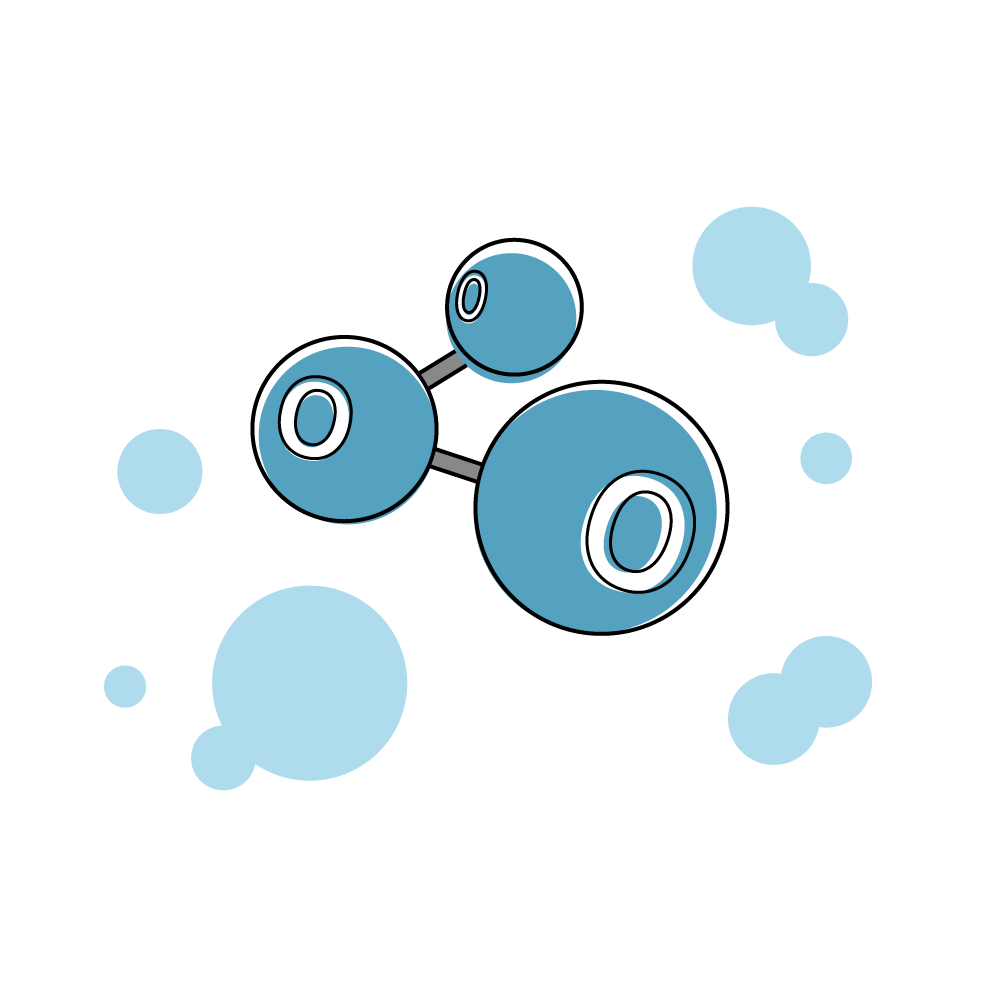
「オゾン」と聞くとどのような印象を持たれるでしょうか?
ニュースや新聞では、オゾンによる健康被害、または環境問題の話題にも登場するため、危険なイメージを持っている方もいるかもしれません。
実はオゾンは、自然界で紫外線から地球を守る「良いオゾン」、私たちの健康を脅かす「悪いオゾン」と、場所や濃度によって性質の異なる二つの側面を持っています。
今回はオゾンが持つ、良い面と悪い面を詳しく見ていきましょう。
オゾンとは「オゾンって何?」で紹介しているように、分子記号(O3)で表される、酸素分子が3つ集まった物質です。
自然界では、主に2つの経路でオゾンが生成されます。1つは、太陽からの紫外線が高層大気中の酸素分子に当たることで、酸素分子が分解され、再び結合してオゾンが生成される経路です。もう1つは、雷の放電によって、酸素分子が分解されて、オゾンになる経路です。
この2つの自然界での生成の仕組みを応用し、UVランプを使った紫外線法や、無声放電法という、人為的にオゾンを発生させる方法でさまざまな場面に利用されています。
■地球を守る「良いオゾン」
地球の成層圏、地上約10〜50kmに位置するオゾン層は私たちにとって不可欠な存在です。
太陽から降り注ぐ有害な紫外線の大部分を吸収し、地上の生物を紫外線によるDNA損傷や皮膚がん、白内障などからまもっています。
オゾン層は、紫外線によって酸素分子がオゾンに変化し、またオゾンが紫外線によって酸素分子に戻るというサイクルをくり返すことで、一定の厚みを維持しています。
■地表の「悪いオゾン」
一方で、地上に近い対流圏で生成されるオゾンは、その性質も発生方法も異なります。対流圏オゾンの主な生成メカニズムは、工場や車から出る二酸化窒素に紫外線が当たると、一酸化窒素と酸素原子に分解され、この酸素原子が酸素分子に結合してオゾンができます。さらに、ここに炭化水素があると、さらに化学反応が繰り返し起きることで、オゾンを生成し続けます。
このオゾンを含む酸化性物質の総称を「光化学オキシダント」と呼びます。
光化学オキシダントは、高濃度になると「光化学スモッグ」として現れ、視界不良や喉への刺激、気道の炎症を引き起こすなど、人体に悪影響を及ぼす恐れがあります。
特に、日差しが強い・気温が高い・風が弱い日は、光化学オキシダントが発生しやすく、注意が必要です。
■人に有益な「良いオゾン」
しかし、地表で発生するオゾンには、人々の生活に役立っている良いオゾンとしての一面もあります。
「オゾンによる脱臭・殺菌の仕組み」で紹介しているように、オゾンのその強力な酸化力は、脱臭・殺菌・ウイルスの不活化などの用途で活用されています。このような用途では、人為的にオゾンを発生させる必要がありますが、人が高濃度のオゾンを吸入しないようなオゾン発生装置を設計することや、適切な換気のもとで利用されることがきわめて重要です。
上記でも紹介したとおり、オゾンが高濃度になると、人体には有害です。特に、呼吸器系への影響が大きく、濃度や暴露時間によっては、深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。オゾン発生器などを導入する場合は、専門家に濃度や暴露時間の設定について相談を行い、適切な管理を徹底することが重要です。
■まとめ
オゾンは、成層圏では私たちを紫外線から守る盾となり、地表では私たちの健康を脅かす存在にもなります。しかし、その強力な酸化力を適切に使えば、脱臭や殺菌、ウイルスの不活化など、私たちの生活の質を高めてくれる有益な存在です。オゾンの二面性を正しく認識し、より安全で快適な生活に役立てていきましょう。